子どもや兄弟姉妹が相続したときの相続税の概算額は?令和4年版早見表
1 はじめに ~ 相続税の計算の流れ ~
(1)相続税の期限は?
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です(相続税法27条1項)。
たとえば、死亡した日が5月20日だとすると、翌年の3月20日が申告の期限となります。
相続税以外の死亡後の手続きの一覧はこちらの記事をご覧ください。
(2)相続税の対象となる財産は?
相続税は、以下の財産が課税対象となります。
①被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(不動産や預貯金や株式など)
②みなし相続財産(生命保険金や退職金 ※一部非課税枠あり)
③相続人や受遺者に対して相続開始前3年以内に生前贈与された財産
④生前贈与を受ける際に相続時精算課税を選択した場合の生前贈与された財産
このうち、④は、相続時精算課税制度を利用した場合のものですので、生前にこの制度を利用していない場合には、①から③の財産を対象に相続税を計算することになります。これらの対象となる財産が多ければ多いほど、税金が増える仕組みになっています。
③の相続人や受遺者に対して相続開始前3年以内に生前贈与された財産は、相続時に存在していなくても、相続税の計算の対象となります。遺産として現存していないのに相続税の対象となるという点が注意点です。しかし、考え方によっては、3年分しか遡って相続税として課税されないということです。そのため、3年より前に110万円の贈与税の基礎控除を利用して生前贈与を活用していれば、贈与税もかかりませんし、相続税もかからず、大きな節税となるため、令和4年現在、課税強化の方向で、制度の改正が検討されています。
(3)基礎控除額とは?
遺産があれば、その遺産にそのまま税率をかけていくというわけではなく、一定の金額を超えなければ、相続税がかからない仕組みとなっています。それが、基礎控除という仕組みで、基礎控除額の計算は以下のとおりです。
3000万円 + (相続人の人数×600万円) = 基礎控除額
そのため、相続人が2人なら、3000万円+1200万円となり、合計4200万円を超えなければ、相続税はかかりません。
(4)早見表の見方
相続税の計算は、①課税対象の財産の金額から、基礎控除額を控除した残額について(課税遺産総額)、②残額が仮に各相続人へ法定相続分どおりに分配されたと仮定した場合の配分された金額に税率をかけて、これにより算出された相続人ごとの税額をいったん合計し(算出税額の総額)、③今度は、この算出税額の総額を、法定相続分ではなく財産が実際に配分された割合に按分して、④さらに、相続人ごとの加算減算の事情を加味して、それぞれの相続人や受遺者が納付する税額を計算していきます。
そのため、分け方や受け手の属性によっても、税金の金額が変わってしまい、複雑です。
このページでは、仮に遺産が法定相続分どおりに分配されたと仮定し、相続人ごとの加算減算の内容としては「配偶者の税額軽減」と兄弟姉妹の「相続税額の2割加算」という2つの制度を適用した上での相続税の合計額を、遺産の額(課税対象となる財産の額)に応じて整理した表を、早見表として紹介します。
兄弟姉妹の法定相続分の詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
「配偶者の税額軽減」の計算例はこちらの記事をご覧ください。
2 子どもが相続人の場合の相続税の金額の早見表
下の表をご覧ください。
遺産の額(正確には冒頭で説明した課税対象となる財産の合計額)が3000万円の行では、すべて、相続税が0円となっております。これは、先に説明した基礎控除額によって、税率をかける元の数字がゼロになっているからです。
同じ遺産の額でも、相続人の人数が増えれば増えるほど、相続税が少なくなっていることがお分かりでしょうか。これも基礎控除額の計算で、相続人1人増えるごとに600万円分の課税対象財産が減るからです。
配偶者が無より有の場合の方が相続税が少ないです。これは、配偶者がいる分だけ相続人の人数が1人多いので基礎控除額も増え、税率をかける前の財産が減るのが1つの理由ですが、それ以上に、配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があるためです。

3 兄弟姉妹が相続人の場合の相続税の金額の早見表
次に、相続人が兄弟姉妹の場合です。
子どもが相続人である場合に比べて、若干、相続税の総額が増えているのがお分かりでしょうか。
これは、兄弟姉妹の相続税は、子どもや配偶者や親に比べて、割加算(1.2倍)となるという個別の加算事由である「相続税額の2割加算」があるからです。
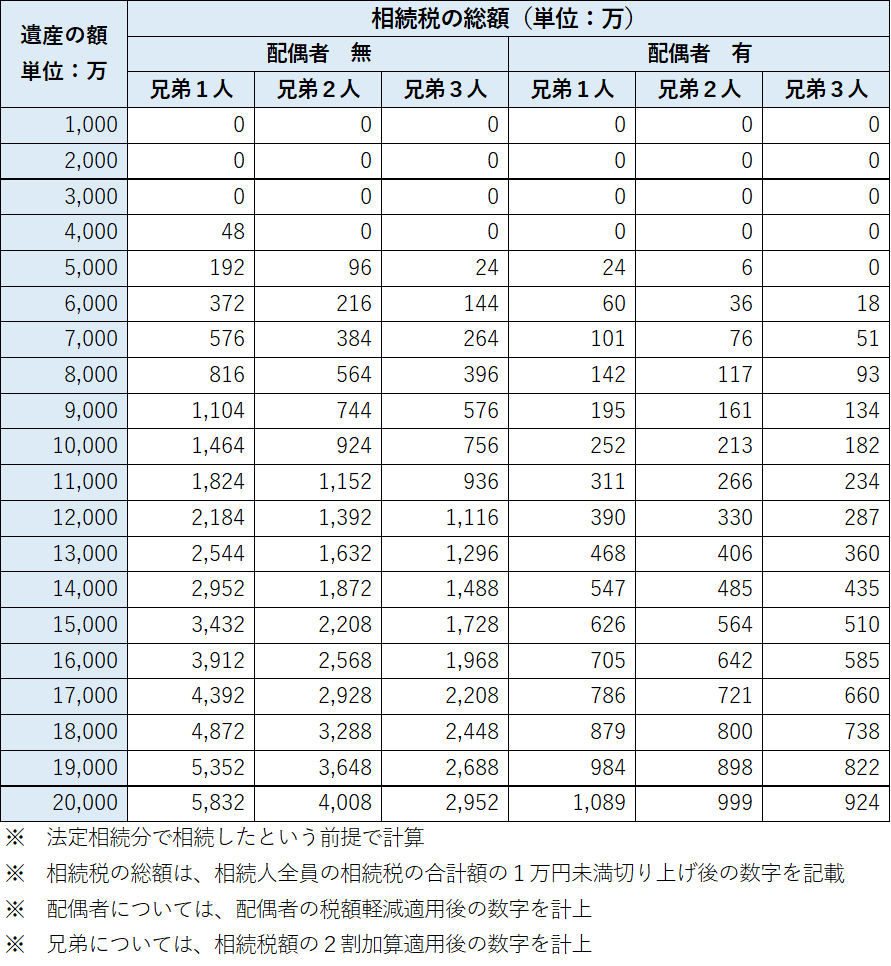
4 相続は税理士と連携できる弁護士へ
相続税の申告が必要な事案においては、税理士が専門となります。しかしながら、上記のように、分け方によっても税金が変わってしまうため、まずは、分け方を決める必要があります。
そのため、もし、相続人間で協議がもめているのであれば、税理士と連携できる弁護士に依頼するのがお勧めです。












